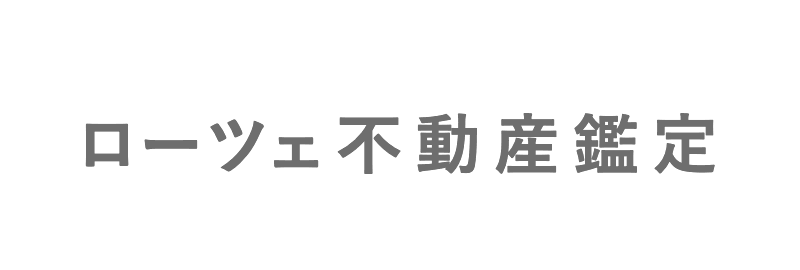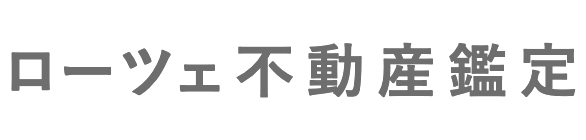土地の所有権が共有状態になっていると処分や利用・管理等において制限が生じるため、トラブルが起きやすいです。
現在は、各共有者間の関係が良好であっても、相続等を契機に当事者の関係が変化し、問題が表面化する可能性もあります。
そこで、このようなリスクを回避するために、共有状態の土地を分筆することによって、複数の土地に分割して分割後の各々の土地について、各共有者が単独所有の状態にする手続きを行うケースがあります。
この手続きは各共有者の持分を根拠に行うのですが、分筆後の各々の土地の単価が概ね同じになるような場合には持分に応じて面積按分して分筆すれば良いでしょう。
例としては下図のようなケースです。
このような場合には、我々、不動産鑑定士が介在する必要はないものと思われます。
但し、以下のような場合には、上の例図のように話は単純ではありません。
このようなケースは単純に持分に応じて面積按分しただけでは、価値的にお互いに1/2ずつの土地を単独所有したとは言えません。
- の場合
所有者Bが取得した土地の形状が旗竿状になっており、所有者Aが取得した整形地の土地に比べ単価が安くなります。したがって、分割後の土地の価値は持分比率に応じて面積按分しただけではイコールになりません。
- の場合
大通りと裏通りに面している二方路地ですが、大通り沿いは容積率200%の指定があり、裏通り沿いが容積率100%に指定されています。指定の境はピンクの線です。
このような場合には大通り沿いで容積率が高い範囲のほうが一般的には単価は高くなります。
所有者Bが取得した土地は細い裏通り沿いに面していて、相対的に低い容積率しか享受できないことから、所有者Aの土地に比べ単価が安くなるばかりか、仮に、接面道路である裏通りの幅員が4m未満の場合、建物の建築の際に建築基準法のセットバックが必要となることもあります。セットバック部分は宅地として利用できないことから、さらに、価値が下がることになります。
最後に当事務所で実際にお手伝いさせていただいた解決事例の一つをご紹介させていただきます。
東京都内で最寄駅から徒歩10分程度の距離にある閑静な低層住宅地域内にある規模2,988㎡の広大な土地が、母親が持分5/6、子が持分1/6の共有状態になっていました。この土地は一体で農園として貸し出されていましたが、母親もまだ若く、相続もだいぶ先であることが予想されることから、子の持分をに対応する部分について、分筆して宅地として利用したいとのご意向で当事務所に相談が来ました。
ただ、この土地ですが、広大であるにもかかわらず、道路付けが悪く、中々、厄介な土地でした。概略図は以下の通りです。
特に、注意しなければいけないのは、下側で対象地に面している公道(建築基準法外道路)にのみしか接面しないような土地として分割を行っても、建物が建てられません。
単純に持分比率で面積按分すると
2,988㎡×5/6=2,490㎡
2,988㎡×1/6=498㎡
となりますが、対象地は面積が広いため、分割の方法も様々のバリエーションが考えられることから、依頼者と何回も打ち合わせをし、意向を探っていきます。
この時、留意しなければならないのが、必ずしも合理的な分け方が、依頼者の意向と同じにならないと言うことです。
この案件については最終的に下図のような形で分筆を行いました。
子の取得した部分は道路付けが悪いので、母が取得した部分に比べ単価が安くなります。また、分割後の面積も比較的大きいため、開発法という手法を適用して価格を求めましたが、その手法を適用する際に作成した開発想定図を見比べても、道路付けの良否に関連して潰れ地の比率が子の取得した土地が大きくなるのも、単価を下げる大きな要因となります。
最後に持分比率で面積按分して土地の分割を行うと分り易く、単純ですが、後に当事者間で不公平が生じることもあります。
単純なケースなのか、鑑定評価額を基に分筆したほうが良いのか等、当事務所に意見を聞くだけ聞いてみるのもご一考かと思います。