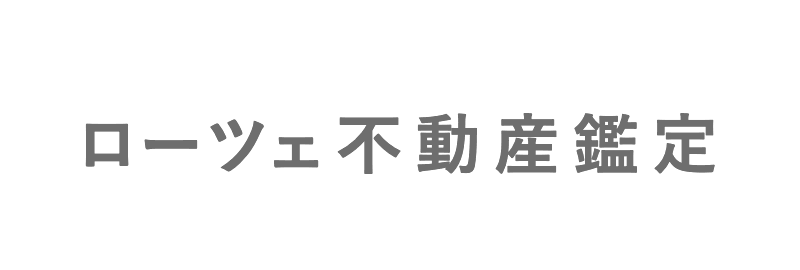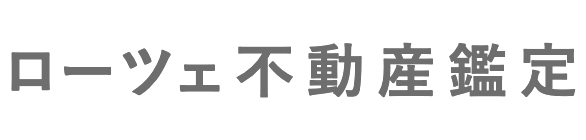相続財産に市街地山林がある場合、一般に下記のフローチャートに沿って評価方法を決定していきます。
評価額の大小は、
通常の宅地比準方式による評価額>近隣純山林価額比準方式による評価額
となりますが、その評価減はかなり大きなものになります(誤解を恐れずに言うならば、宅地比準方式による評価額に比べ近隣純山林価額比準方式による評価額はただ同然になることが多いです)。
近隣純山林比準方式により評価するためには、上記の(1)及び(2)に該当する必要があるわけですが、その是非を判定するために、当事務所の調査報告書を活用していただけます。
なお、分り易く言うと(1)に該当する場合とは、物理的に宅地転用が不可能な場合で、(2)に該当する場合とは、売却収入から造成費を控除した額がマイナスになる場合や純山林としての価額を下回る場合で、所謂、宅地転用しても投資採算性が全く合わないケースです。
なお、(1)に該当しそうな場合には、報告書の作成は比較的簡易なもので作成できることありますが、(2)に該当するか否かを判定する場合の報告書は、作成に当たり、かなり大がかりになることが多いです。
以下、当事務所で関与させていただいた(2)に該当するか否かを判断した事例を一つ紹介させていただきます。
対象地は神奈川県内の面積約2,000㎡程度の市街地山林でした。
現況は以下の通りです。
傾斜の多い規模の大きい市街地山林ですが、対象地は面積が大きく奥行きもあるので、採算を度外視すれば宅地造成が出来るはずで、そうすると、物理的に宅地造成が出来ないとまでは言えません。
依頼者からのヒヤリングによれば、役所等にも引き取ってもらえず、買い手からの引き合いも全くないとのことでしたが、その辺の事情を口頭・書面等で説明しても税務署に対して説得力は担保できません。
したがって、客観的な資料として、経済合理性がないかどうか否かを探っていきます。具体的には、鑑定評価方式の一つである開発法を適用していきます。
開発法は以下のような式で表せます。
この手法は、対象地に係る投資採算性に着目した手法です。
(開発法)
本件対象地は傾斜も多く、規模も大きいため、普段お世話になっている宅地開発業者に開発想定図の作成と造成費の見積もりを依頼しました。
結果として、下記の試算表を参照すると分かるとおり、収支はマイナスとなり、宅地造成に経済的合理性がないことが分かります。
結果として、対象地は上記(2)に該当すると判断し、報告書を作成、提出させていただきました。
市街地山林は、実際に売りに出しても買い手が見つからなかったり、二束三文の価格でしか売れなかったり、有効活用も困難と所有者の悩みの種となっている場合がかなり多いです。また、条件さえそろえば、このような方法で評価額がかなり減額できることを知らずに通常の宅地比準方式で評価して割高な相続税や贈与税を払われている方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
もしかして、自分の所有している市街地山林が当てはまるのでは?と心当たりのある方はお気軽にご連絡下さい。