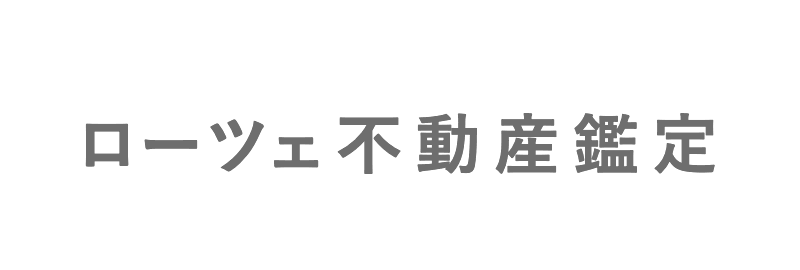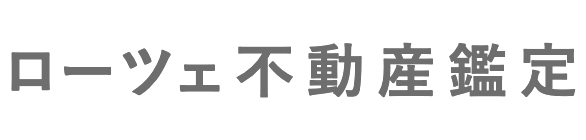不動産を法人に貸している場合、その貸付形態が「使用貸借」なのか「借地権の設定」なのか──これは相続税評価において極めて大きな違いを生みます。特に、被相続人が土地を所有し、同族法人がその土地に建物を所有していた場合、「借地権が認定されるかどうか」で評価額に大きな影響が出ます。
今回は、そんな論点を扱った2つの裁決(熊本国税不服審判所平成16年9月10日裁決、大阪国税不服審判所平成9年2月17日裁決)をもとに、法人との土地の貸借関係がどう評価されるかを実務的に解説します。
目次
1.2つの裁決の比較と事実関係
| 裁決 | 所有関係 | 支払地代 | 無償返還届 | 税務署側主張 | 結果 | 評価額の動き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本国税不服審判所 平成16年9月10日(熊裁(諸)平16-5) | 土地:法人/建物:被相続人 | 固定資産税相当額 | なし | 借地権あり → 相続財産に加算 | 認容 | 相続財産増加 |
| 大阪国税不服審判所 平成9年2月17日(大裁(諸)平8-58) | 土地:被相続人/建物:法人 | 固定資産税相当額 | なし | 借地権あり → 底地評価へ修正 | 認容 | 相続財産減少 |
このように、2つの事案ではいずれも「固定資産税相当額のみを支払っていた」という点では共通していますが、相続財産の評価方向は真逆です。
その理由を整理していきましょう。
2.「使用貸借通達」は法人には適用されない
財産評価基本通達では、親族間などの無償貸付について「使用貸借」として借地権は評価しない取り扱い(いわゆる「使用貸借通達」)が存在します。
これは、あくまで「個人間」での無償使用貸借を前提としており、例えば親が子に土地を無償で貸しているようなケースで適用されます。
しかし今回のように、貸主・借主のいずれかが法人である場合は、この使用貸借通達の適用対象外となります。法人は契約行為において独立した経済主体であるため、形式上無償であっても、「本当に無償性があるのか」「経済的利益の供与ではないのか」といった点が厳しく問われます。
また、法人との間では無償返還の届出がない限り、借地権の設定があったと推定される可能性が高く、課税リスクが非常に高くなります。
今回の裁決でも、いずれのケースも無償返還の届出がされておらず、税務当局は借地権が認定されることを前提に評価を行いました。
つまり、法人が関与する使用貸借的実態には、使用貸借通達という“安全網”はなく、最初から「借地権が存在する」という前提で評価リスクを想定することが必要なのです。
3.借地権が「設定されている」ことと「借地権価格が発生している」ことは別
実務でよく誤解されるのが、「借地権が設定されている=借地権価格が発生する」と思い込む点です。
しかしこれは評価実務上も、不動産鑑定評価基準上も明確に区別されています。
「借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではなく、…(中略)…借地権が建物の取引に随伴して取引の対象となっている都市又は地域があること」(不動産鑑定評価基準抜粋)
つまり、法律上借地権が成立していても、その地域に借地権の取引慣行がなければ、経済的利益(借地権価格)は評価されないというのが実務上の考え方です。
この点を整理すると以下のようになります:
- 借地権が設定されているかどうか(=法律関係)
- 法人が関与していれば、設定されているとみるのが原則
- 借地権価格が発生しているかどうか(=取引慣行・経済的実体)
- 地域の取引慣行により左右される
つまり、借地権の存在が直ちに帳簿上の資産や評価額に反映されるわけではなく、市場実態と経済合理性を加味して判定すべきということです。
第4章|無償返還の届出がない場合の評価リスクと「取引慣行」の意義
4-1.無償返還の届出がないと「借地権あり」と判断されやすい
法人に土地を貸し付けている場合、その土地に設定された借地権について「無償返還に関する届出書」が提出されていないと、税務上は借地権があるものとして取り扱われる可能性が極めて高くなります。
本来、この届出書は、借地権の設定時に「将来無償で土地を返還する意思があること」を課税庁に示すためのものです。提出されていれば、借地権の課税(いわゆる認定課税)を回避できます。
しかし今回の熊本・大阪両事案では、いずれも届出書が提出されていなかったため、課税庁は「借地権が設定されている」と判断し、借地権価格の評価へと進みました。
なお、本来的には両事案は借地権設定時に借地権の取引慣行があれば(借地権価格の存在が認識されれば)、一時金の授受がなくても認定課税されるべきところ、これがスルーされていることが、事案を複雑化させている遠因になっています。
4-2.「借地権の取引慣行」がなければ価格は発生しない
ただし、借地権が「設定されている」と認定されたとしても、必ずしも借地権価格が発生するわけではありません。
その価格の有無は、地域における借地権の取引慣行が存在するかどうかによって決まります。不動産鑑定評価基準でも、賃借権の価格はその実体的内容や取引の実情に即して判断するべきであるとされています。
たとえば次のような簡易的な指標が判断材料になります:
- 路線価図や倍率表で借地権割合が30%以上と明示されている地域
→ 取引慣行あり → 借地権価格が発生 - 借地権割合の表示がない地域
→ 取引慣行なし → 借地権価格は評価不要
(但し、底地=貸宅地については、借地権割合20%として計算した借地権の価額を控除して評価することに注意)
つまり、借地権が設定されていたとしても、地域的な実態によっては価格評価の対象とならないケースもあるのです。
なお、今回の事案については、熊本の案件の対象地は借地権割合40%の地域内にあり、大阪の案件の対象地は借地権割合70%の地域内にありました。
第5章|まとめ──借地権の「設定」と「価格」は分けて考える
今回の2つの裁決(熊本・大阪)を通じて、次のような重要な実務的示唆が得られます。
- 法人が関与する土地の無償貸付は、原則として「使用貸借通達」の適用外
→ 借地権が設定されているものとして扱われるリスクが高い - 借地権が設定されていても、「借地権価格が発生するかどうか」は別問題
→ 地域における借地権の取引慣行が判断の鍵となる - 無償返還の届出書が提出されていない場合は、税務上の借地権評価が前提に
→ 相続財産の増減リスクを伴う - 熊本事例では借地権が加算され、相続財産が増加
大阪事例では借地権が控除され、底地として評価=相続財産が減少
(その背後に同族法人の株価の増減もあることに注意) - よって、相続税評価においては:
- 借地権の設定の有無(=法的整理)
- 借地権価格の発生の有無(=取引慣行)
この二軸で冷静に整理することが不可欠
■ 借地権の評価判断を「設定の有無」と「価格の有無」の両軸から整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 熊本裁決 | 大阪裁決 |
|---|---|---|
| 借地権の設定有無 | 有(法人所有地) | 有(建物所有法人) |
| 無償返還の届出書 | 提出なし | 提出なし |
| 地域の借地権割合 | 40% | 70% |
| 借地権価格の発生 | 有(価格あり) | 有(価格あり) |
| 税務署の評価 | 借地権価格を相続財産に加算 | 借地権控除→底地評価に修正 |
| 評価影響 | 相続財産増加 | 相続財産減少 |
このように、借地権評価は「法的な設定の有無」と「経済的な価格の有無」の両面から慎重に判断する必要があります。とくに法人が関与するケースでは、無償返還の届出の有無と地域的な取引慣行がリスク判断の鍵を握ります。