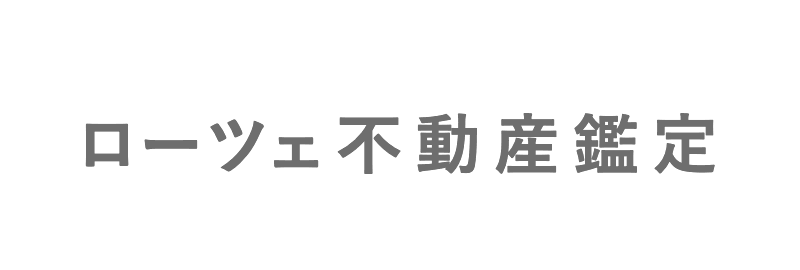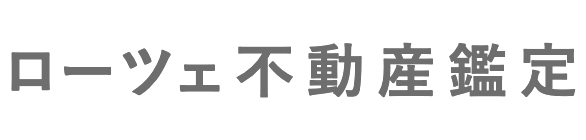「通達に従っていれば大丈夫」──相続税評価の現場で、こんな言葉を耳にすることは少なくありません。
しかしその“安心”は、本当に揺るぎないものなのでしょうか?
2022年の札幌事件(最高裁令和4年4月19日判決)では、税務署側が通達評価に異議を唱え、「財産評価基本通達 総則6項」を発動するという異例の展開が起こりました。これは、「通達は時価評価の基準である」とされる従来の運用に、大きな一石を投じるものでした。
本記事では、不動産鑑定士の視点から、この事件の実態と評価上の論点を丁寧に読み解きながら、相続税評価の「制度の裏側」に迫ります。特に、資産税を扱う税理士や相続実務に携わる専門家にとって、看過できない判例です。
1.はじめに──通達評価は本当に「時価」なのか?
1-1.相続税実務における「通達評価」という標準
相続税や贈与税における財産評価では、国税庁が定める「財産評価基本通達(以下、評価通達)」に基づく評価方法が広く用いられています。特に不動産の評価では、路線価方式や倍率方式など、通達に沿った評価が“原則”とされてきました。
税理士実務でも、「通達に準拠した評価=適正な申告」と認識されている場面が多く、相続人がそのまま受け入れてしまうことも少なくありません。
実際、通達通りに評価を行っていれば、税務調査で問題になることは少なく、「申告実務の安全装置」として機能している面もあります。
1-2.「通達=時価」ではないという裁判所の判断
しかし、ここに盲点があります。評価通達は、あくまで“画一的なルール”であって、すべてのケースにおける「時価」を完全に反映するものではありません。
特に、実際の市場価格や不動産鑑定評価額と大きく乖離してしまうようなケースでは、「通達評価額=時価」とは言い切れなくなるのです。
札幌事件では、まさにこの「通達評価の限界」が争点となりました。税務署は、評価通達の枠組みで算出された評価額が、市場価格と著しく乖離していたことから、「通達評価は著しく不適当である」として、総則6項を発動しました。
2.札幌事件とは──税務署が6項を発動した異例の構図
■ 札幌事件の時系列
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 平成20年8月19日 | 被相続人Aと原告Eが養子縁組 |
| 平成21年1月30日 | 甲不動産を取得(購入額:837,000,000円、借入:M信託銀行630,000,000円) |
| 平成21年12月25日 | 乙不動産を取得(購入額:550,000,000円、借入:M信託銀行379,000,000円、訴外A47,000,000円) |
| 平成24年6月17日 | 相続開始(甲・乙不動産は遺言により原告Eが取得) |
| 平成25年3月7日 | 原告Eが乙不動産を売却(売却価額:515,000,000円) |
| 平成25年3月11日 | 相続税申告(評価通達による評価) 甲土地:113,676,734円、甲建物:86,364,740円(小計200,041,474円) 乙土地:58,162,741円、乙建物:75,502,026円(小計133,664,767円) 合計:333,706,241円 |
| 平成28年2月17日 | 札幌国税局長が国税庁長官に上申 |
| 平成28年3月10日 | 鑑定評価による指示: 甲:土地308,000,000円、建物446,000,000円(合計754,000,000円) 乙:519,000,000円 合計:1,273,000,000円 |
| 平成28年4月27日 | 本件各更正処分 |
2-1.収益物件を借入で購入した資産圧縮スキーム
本件の被相続人は、相続開始前に東京都内の大型収益用不動産を2件(以下、甲不動産・乙不動産)取得しています。
・甲不動産:平成21年1月30日取得
・乙不動産:平成21年12月25日取得
・相続開始日:平成24年6月17日
いずれも取得から相続開始まで数年の期間があるため、「被相続人による死亡直前の取得」とは言えないものの、購入資金は多額の借入(約10億円)によって調達されており、いわゆる“資産圧縮スキーム”が存在していたといえます。
このスキームは、「借入を使って大型不動産を購入し、通達評価で低めの相続税評価額を設定しつつ、債務控除によって純資産を圧縮する」という考えに基づくものです。
■ 甲不動産および乙不動産の明細
| 名称 | 所在地 | 地目 | 地積(㎡) | 用途 | 構造 | 床面積 | 取得日 | 譲渡日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲不動産(甲土地・甲建物) | 杉並区 | 宅地 | 378.67 | 共同住宅・店舗 | RC造8階建 | 延1,408.86㎡(1F~8F) | 平成21年1月30日 | 継続所有 |
| 乙不動産(乙土地・乙建物) | 川崎市 | 宅地 | 281.65 | 駐輪場・居宅 | RC造7階建 | 延928.04㎡(1F~7F) | 平成21年12月25日 | 平成25年3月7日 |
2-2.通達評価と市場価格に大きな乖離が発生
相続時の申告では、甲・乙の不動産はいずれも通達評価により算出された額で申告されました。ところが、相続後、相続人の一人が乙不動産を第三者に売却した結果、その売却価格が申告時の通達評価額を大幅に上回ることが明らかになりました。
これにより、「実際には高額な資産を通達評価によって過小評価し、債務控除で課税ベースを圧縮した」とする税務署の判断が動き出すこととなったのです。
2-3.税務署が総則6項を発動
財産評価基本通達 総則6項は、「通達に基づいて評価した結果が著しく不適当であると認められる場合には、他の合理的な方法により評価する」と定めています。
本件では、通達評価と市場価格の差異が著しい点、相続直後の売却実績がある点、さらに借入による資産圧縮の意図が強く読み取れる点などを総合的に考慮し、税務署は「通達に従っていても、実態と乖離していれば6項で是正できる」として、6項を発動したのです。
3.6項発動を裁判所はどう見たのか?
3-1.一審・二審の判断
納税者側は、「通達評価に基づく申告は合法であり、税務署がこれを否定するのは不当である」と主張しました。しかし、一審(札幌地裁)・二審(札幌高裁)ともに、税務署の6項適用を正当と判断しました。
評価の「形式的な正しさ」ではなく、「実態と整合しているか」が重視された点が、極めて実務的な示唆に富むポイントです。
3-2.最高裁の判断とその意義
そして、令和4年4月19日、最高裁判所は本件について正式に判決を下しました。
判決では、税務署の6項適用を適法と認め、通達評価による申告が市場実態と乖離している場合には課税処分が認められると判断されました。
これにより、「通達に従えば安心」というこれまでの実務慣行に一石を投じる内容となり、税理士や納税者に大きな影響を与えています。
4.何が問題だったのか?──評価の形式と実態の乖離
4-1.通達評価の“機械的適用”では見逃される実態
従来、通達評価における路線価方式や倍率方式は、ある種「定型的な安全策」として扱われてきました。しかし、札幌事件ではこの“形式的な正しさ”が覆されたことになります。
・市場価格:実勢価格、売買実績
・通達評価:公的ルールに基づく画一的評価
この両者が著しくかけ離れていた場合、税務当局は「通達評価では実態を反映していない」と判断できる根拠を持ちうる、ということです。
■ 甲不動産および乙不動産の評価額比較
| 不動産名 | 通達評価額(①) | ①/②(購入額比) | 購入価額(②) | 売却価額(③) | ①/③(売却額比) | 鑑定評価額(④) | ①/④(鑑定額比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲不動産 | 200,041,474円 | 23.89% | 837,000,000円 | ― | ― | 754,000,000円 | 26.53% |
| 乙不動産 | 133,664,767円 | 24.30% | 550,000,000円 | 515,000,000円 | 25.95% | 519,000,000円 | 25.75% |
| 合計 | 333,706,241円 | 24.05% | 1,387,000,000円 | ― | ― | 1,273,000,000円 | 26.21% |
4-2.資産圧縮目的とみなされた場合のリスク
本件では、被相続人が生前に借入を通じて大型不動産を取得し、結果的に相続税評価額が大幅に下がっていたという構図がありました。
仮に、
- 低評価の不動産で申告
- 実際には高値で売却
という結果が生じていれば、税務署から「租税回避目的の取引」とみなされかねず、6項適用のリスクが現実のものとなるのです。
5.まとめ──通達評価を“盲信”しないために
5-1.「通達に従えば安心」はもはや通用しない
札幌事件は、「評価通達に基づく申告であっても、無条件に適正とは認められない」という新たな実務基準を提示しました。
今後は、通達評価額と市場価格・実勢価格の乖離がある場合、「形式に従うだけでは足りない」時代に突入したといえるでしょう。
5-2.専門家の関与と事前対応の重要性
税理士や不動産鑑定士に求められるのは、「制度の理解」だけでなく、「評価の背景にある意図やリスクの分析」です。
今後の相続実務では、
- 借入を使った収益不動産取得
- 評価額と売却額の著しい乖離
- 過度な債務控除
──これらの要素が揃う場面では、早期のリスク分析と専門家による妥当性の検証が不可欠です。
通達の限界を踏まえた「実態に即した評価」が、今後ますます重要になるでしょう。