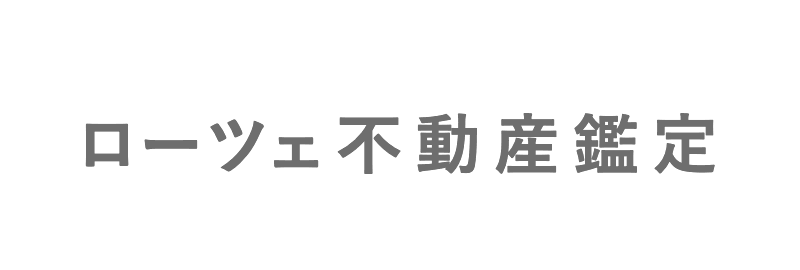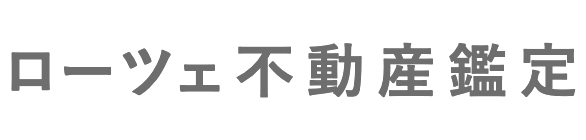「借金してタワマンを買えば相続税が減る?」──かつて話題となったこの節税手法が、ついに制度として封じられました。
その転機の一つとなったのが、平成23年7月1日裁決(東裁(諸)平23-1)です。
この事例では、相続直前に購入したタワーマンションに対して財産評価基本通達による評価額が否認され、課税庁が総則6項を発動。審判所もこれを認め、通達評価ではなく取得価額による課税が是認されました。
その後、令和6年1月1日以降の相続・贈与について国税庁が通達を改正し、いわゆる「タワマン節税」に制度的な歯止めがかけられることとなります。
本記事では、この裁決事例と通達改正の背景をふまえ、評価実務がどのように変わったのかを不動産鑑定士の視点で詳しく解説します。
目次
第1章 「タワマン節税」が注目された理由
相続税対策として、かつて一定の富裕層の間で広く活用されていた手法があります。それが、いわゆる「タワマン節税」です。タワーマンションの特性を活かし、相続税の評価額を意図的に圧縮するこのスキームは、長年にわたって“合法的な節税手段”として黙認されてきました。
この手法の肝は、評価方法と債務控除の仕組みにあります。
相続税の評価は、財産評価基本通達に基づいて行われ、建物については固定資産税評価額、土地については「敷地権割合」で按分されるため、市場価格よりも大幅に安く評価されるのが一般的です。
特にタワーマンションの高層階・高価格帯の物件では、実勢価格の3〜4割程度にまで評価額が下がるケースも多く見られました。
これに加えて、タワーマンションの購入資金を借入でまかなえば、その債務は相続財産から差し引かれます。つまり、高額なマンションを借金で買えば、資産としての評価額は小さく、借金の控除は大きくなるという、評価と債務控除の“逆転現象”が起きるのです。
具体的なケースで考えてみましょう。
たとえば、ある被相続人が亡くなる直前、相続人が2億円の借入でタワーマンションを購入したとします。
通達評価額が6,000万円程度、他の財産が1億円、借入金が2億円だとすると、
6,000万円(マンション評価額)
+ 1億円(その他の財産)
- 2億円(借入金)
= ▲4,000万円
という計算になり、相続税の課税対象はゼロとなってしまうのです。
このような構造を利用したスキームは、脱法的な行為とは言えないものの、課税の公平性を大きく損なうとして次第に問題視されるようになりました。
特に、平成20年代以降はこの手法を解説する書籍やセミナーも数多く出回り、一部の相続対策コンサルタントや富裕層にとっては“常識”のような位置づけにもなっていました。
しかし、本質的には評価制度の“抜け穴”を突いたものであり、通達に従っていれば適正とされる現行制度の信頼性そのものが問われるようになっていったのです。
このような状況下で、税務当局はついに動き始めます。
個別事案において、通達評価額を否認し、通達の例外規定である「総則6項」を発動する事例が出始めたのです。
そしてその第一の象徴的な裁決が、平成23年の東京審判所による「通達評価否認」でした。
第2章 【実例】東京審判所が否認した通達評価(平成23年裁決)
2-1.2億9,300万円の購入 → 通達評価額5,801万円 → 売却2億8,500万円
本件で注目されたのは、相続開始直前に購入された高額タワーマンションです。納税者は被相続人の入院中に、被相続人名義に無断で被相続人名義で媒介契約を締結し、平成19年8月4日に2億9,300万円でマンションを購入しました。相続開始はその約1か月後。評価時点ではまだ築浅の高層マンションであり、通達に基づく評価額は5,801万8,224円とされていました。
ところが、相続発生後、1年足らずで、このマンションは第三者に2億8,500万円で売却されていました。購入価額と売却価額がほぼ同額である一方、相続税申告における通達評価額との差は2億2,000万円以上に及びます。つまり、形式的には合法な通達評価であっても、実際には大きな節税効果を狙った評価圧縮であったと読み取ることができます。
この取引の背景には、「相続税を減らすために購入した」と見なされてもおかしくない事情がありました。被相続人の意思関与が不明確であり、購入にあたっての資金負担も含めて相続人が主導していたことがうかがえます。また、物件の購入から相続開始、そして第三者への売却までが非常に短期間に集中しており、経済合理性ではなく税負担軽減を目的とした取引である可能性が高いと判断されました。
2-2.課税庁が通達6項を発動、審判所が是認
このような乖離に対し、課税庁は財産評価基本通達 総則6項を発動。「通達に基づく評価額では著しく不適当」として、取得価額をもとに評価する方が合理的であると主張しました。
審判所もこれを支持し、「節税目的の取引であり、形式的に通達に従っていても、経済的実質を無視する評価は認められない」と明言。通達評価を否認し、課税庁側の主張を容認しました。
この裁決は、通達評価が絶対ではないことを明確に示した最初期の実例として、実務に大きなインパクトを与えることとなりました。
✅ 【時系列表】平成23年 東京裁決におけるタワマン節税否認事例
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 平成19年7月4日 | 被相続人が入院 |
| 平成19年8月1日 | 納税者が被相続人に無断で、被相続人名義で本件マンションの媒介契約を締結 |
| 平成19年8月4日 | 本件マンションの購入(購入価額:2億9,300万円) |
| 平成19年9月末 | 相続開始 |
| 平成19年11月13日 | 納税者が本件マンションの相続登記を行う |
| 平成20年2月2日 | 本件マンションについて一般媒介契約を締結(売却のため) |
| 平成20年7月23日 | 本件マンションを2億8,500万円で売却 |
| 平成20年8月29日 | 本件マンションの購入者は3億1,500万円で転売 |
第3章 否認事例の増加と“通達の限界”
平成23年の東京裁決以降、全国の税務現場では、タワーマンションを活用した評価圧縮に対して、課税当局が財産評価基本通達6項を根拠に是正を試みるケースが増加しました。特に、相続開始直前に高額な不動産を借入で取得するなど、税務上の経済合理性が乏しい取引については、「節税目的が明白」と判断されやすく、通達による評価額が否認される傾向が強まっていきました。
実務上、通達6項の発動には高いハードルがあります。というのも、通達6項は「通達の適用が著しく不適当であると認められる特別の事情がある場合」に限り、他の合理的な方法による評価を許容するという、いわば“最後の手段”です。課税当局が6項を発動するには、評価乖離の程度だけでなく、納税者側の意図、取引時点の状況、資金の流れなど、多角的な実態分析が求められます。
一方で、課税庁による6項の適用が増えれば増えるほど、現場では次のような課題も浮上してきました。
- 同様の事例で評価が認められるか否かが「担当官の裁量」に依存してしまう
- 否認の可否が「タイミング」や「地域」などに左右され、納税者間の公平性に欠ける
- 形式上通達に従っていればセーフと信じていた納税者・税理士との認識ギャップが拡大
つまり、通達6項の適用は本来例外的であるはずが、実務上は制度の“抜け道”をふさぐための恒常的な対応策となりつつあり、制度としての限界が露呈し始めたのです。
こうした背景から、国税庁内部でも「個別対応では追いつかない」「評価方法そのものに構造的な見直しが必要」との認識が強まり、ついに制度改正への検討が本格化していくこととなりました。
第4章 【令和6年改正】タワマン評価に「補正率」導入
4-1.制度改正の背景と内容
東京裁決以降、通達6項の適用によって個別事案の是正が図られてきましたが、それだけでは抜本的な解決には至りませんでした。「通達評価そのものが現代の市場実態と乖離しているのではないか」という問題意識は、税務当局内外で年々強まっていきました。
こうした流れの中で、ついに令和6年1月1日以降の相続・贈与について、国税庁は区分所有建物の相続税評価方法に関する通達を改正しました。新たに導入されたのが「区分所有補正率」です。
この補正率は、通達評価額に一定の割合(=補正率)を乗じて、評価額を時価の6割程度に近づけることを目的とした制度です。これにより、従来のような評価圧縮による過度な節税を抑制する効果が期待されています。
たとえば従来、通達評価額が6,000万円だった築浅のタワーマンションが、新制度下では補正率1.2が適用されることで、評価額が7,200万円に上昇する──このように、実態に即した評価への是正が機械的に行われる仕組みです。
なお、補正率の導入はすべての区分所有建物に一律適用されるわけではありません。あくまで**「新築・高層・高層階・容積率の高い物件」などに該当する場合に限り、補正が適用される**点が実務上のポイントです。
4-2.具体的な補正率の算出方法と実務上の留意点
補正率は、登記事項証明書に記載された複数の項目をもとに算出されます。具体的には以下の情報が必要です。
- 建物の総階数
- 対象住戸の所在階
- 築年数
- 専有部分の面積
- 敷地面積
- 敷地権の割合
これらを入力するためのExcelシートが国税庁から公開されており、納税者自身でも試算が可能です。ただし、登記事項の読み取りには一定の専門知識を要するため、評価実務では税理士や不動産鑑定士の協力が不可欠です。
💡 参考リンク:補正率の計算明細書(Excel)はこちら(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/xlsx/0023011-042.xlsx
また補正率が「1.0未満」となることはなく、評価額が現行より下がることは制度設計上想定されていません。その意味でも、今回の通達改正は明確に“節税抑止”の方向に舵を切ったものと位置づけられます。
第5章 これからの評価実務はどう変わるか?
5-1.形式だけの節税はリスクに直結
今回の通達改正により、タワーマンションを利用した極端な節税スキームは制度的に封じられました。従来のように「評価通達に沿っていれば安全」という考え方は、今後ますます通用しなくなると見られています。
ただし、補正後の評価額であっても、依然として時価より2〜3割程度低い水準であるケースも存在します。つまり、節税余地そのものがゼロになったわけではありません。物件によっては、補正率が小さく、旧来通りの評価額が維持される場合もあります。
だからこそ、今後の評価実務では「この物件に補正率がかかるか」「どの程度の補正率が想定されるか」を事前に見極める力が求められます。制度を把握していないまま申告を行えば、後から否認されるリスクも高まるため、「知らなかった」では済まされない時代になったといえるでしょう。
また、仮に補正率が適用されない物件であっても、相続直前の不自然な取得や評価乖離が大きい場合には、引き続き通達6項が発動される可能性があります。今回の制度改正はあくまで「仕組みの標準化」であり、「6項適用の終息宣言」ではありません。
5-2.評価の実質性と専門家連携の重要性
今後の相続税評価では、「通達の機械的な適用」から、「市場実態や取引背景を踏まえた評価」へのシフトが加速していきます。この変化に対応するには、納税者自身だけでなく、評価に携わる専門家の連携が不可欠です。
具体的には、次のような場面で税理士と不動産鑑定士の協業体制が効果を発揮します。
- 区分所有補正率の対象となるか否かを事前判断する場面
- 通達評価額と実勢価格との乖離が大きく、6項適用リスクがある場合
- 鑑定評価と通達評価を併用し、リスク説明や対税務署対応を行う場面
また、補正率計算の基となる登記事項の読解には、建築・不動産に関する実務知識が求められることもあり、税務・不動産の垣根を超えた連携体制が理想的といえます。
「評価額を下げる」ことがゴールではなく、「合理性のある、否認されない評価を構築する」ことが重要であり、そのための専門家の関与こそが、相続人・依頼者の安心につながる時代になっています。
まとめ
タワマン節税をめぐる議論は、平成23年の東京裁決に端を発し、ついに令和6年の通達改正というかたちで制度的な決着を迎えました。
これまで通達6項を使った個別の是正が繰り返されてきた背景には、「通達評価が市場の実態を適切に反映していない」という根本的な問題がありました。今回の改正は、その構造的なゆがみに制度として対応した、非常に大きな転換点といえます。
一方で、今回の補正率導入により節税スキームが封じられたとはいえ、すべてのケースで課税が強化されるわけではありません。補正率が適用されない物件もあれば、通達評価額と時価との間に引き続き差が生じるケースも存在します。
つまり、制度が変わったからといって「すべての評価が自動的に適正になる」わけではないのです。むしろこれからは、評価の根拠や背景を適切に説明できる体制──すなわち実質に即した評価+専門家の関与によるリスクコントロールがより重要になります。
相続税評価は、単なる「計算」ではなく「判断と説明」が問われるフェーズに入っています。不動産鑑定士や税理士といった専門家が連携し、通達の形式と市場の実態を橋渡しすることが、これからの納税者の安心と税務リスク回避に直結する時代が始まったのです。