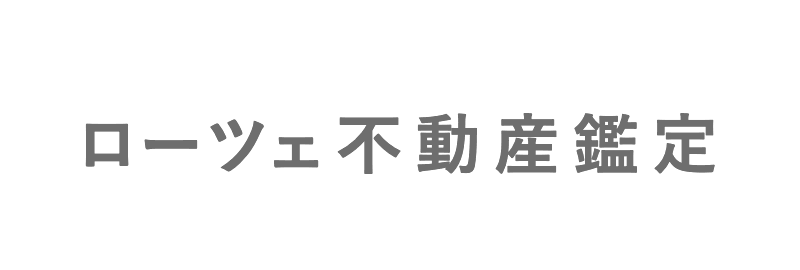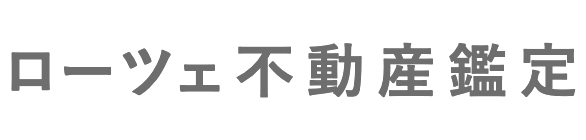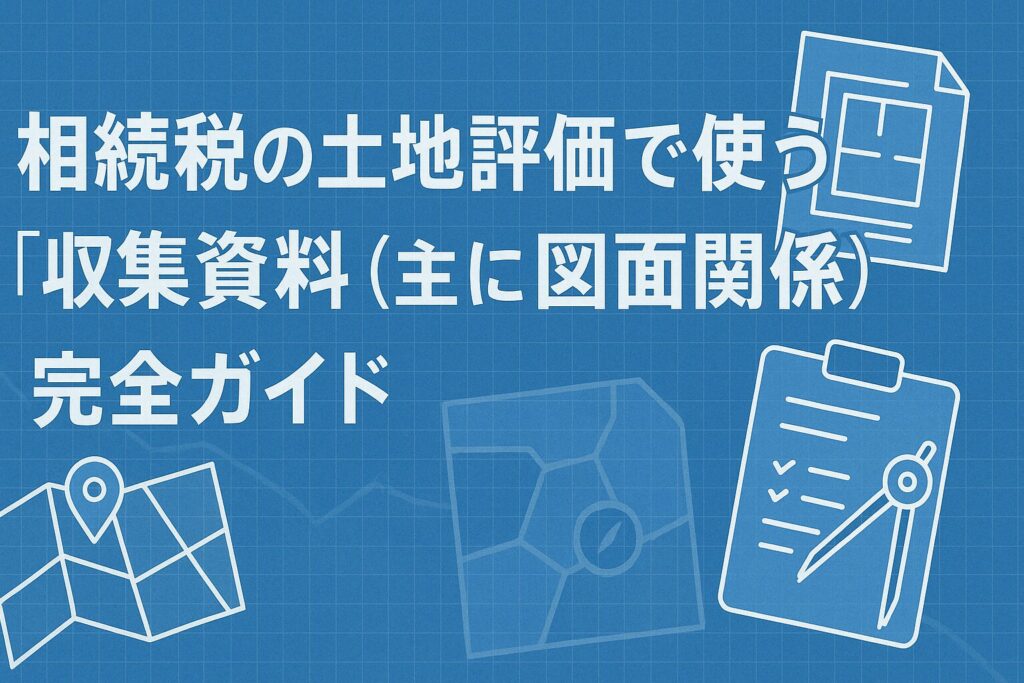
相続税の土地評価を行う際、正確な評価をするためには「図面(地図)」の収集が欠かせません。
しかし、実際の現場では「どの図面が必要なのか?」「どこで入手できるのか?」が分からず、評価が遅れたり、誤った評価につながったりすることも。
本記事では、不動産評価の専門家である不動産鑑定士の立場から、相続税評価に必要な図面の種類と取得方法、それぞれの役割を、初心者にも分かりやすく解説します。
目次
目次
- 1. 相続税評価に「地図・図面」が必要な理由
- 1-1. 評価の出発点は「土地の特定」
- 1-2. 通達評価でも「資料の裏付け」が求められる
- 1-3. 税務署への説明資料にもなる
- 2. 相続税評価に使う主な図面・資料と取得方法
- 2-1. 法務局で取得する図面(登記情報)
- 2-2. 自治体で取得する図面・帳票
- 2-3. 民間サービスで取得できる地図資料
- 3. 図面の使い分けと組み合わせのポイント
- 3-1. 地積測量図がない場合の代替手段
- 3-2. 複数の図面を組み合わせてリスクヘッジ
- 4. よくある失敗と注意点
- 5. 図面収集を専門家に依頼するという選択肢
- 📌まとめ|図面・地図資料の取得先と役割一覧
1. 相続税評価に「地図・図面」が必要な理由
1-1. 評価の出発点は「土地の特定」
土地の価値を正しく評価するには、まずその土地がどこにあり、どのような形状かを把握しなければなりません。図面は、その土地を「評価対象」として特定するための基礎資料です。
1-2. 通達評価でも「資料の裏付け」が求められる
路線価方式や倍率方式など、財産評価基本通達に基づく評価であっても、評価単位・地目・接道状況といった判断には図面が不可欠です。
1-3. 税務署への説明資料にもなる
税務署からの照会や指摘があった場合、評価の根拠として図面があるかどうかで、対応の説得力が大きく変わります。
2. 相続税評価に使う主な図面・資料と取得方法
2-1. 法務局で取得する図面(登記情報)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
地番・地目・面積・所有者などの基本情報を確認。オンラインでも入手可能。
※必ず、一緒に共同担保目録をとりましょう。場合によっては、名寄帳や固定資産税課税明細に出てこない私道持分などの非課税財産が把握できる場合があります。 - 公図
土地の位置関係や隣接地との境界を大まかに把握。オンラインでも入手可能。 - 地積測量図
実測による正確な面積・形状を示す。ある場合は必須。オンラインでも入手可能。
2-2. 自治体で取得する図面・帳票
- 名寄帳、固定資産税課税明細(資産課税課)
相続財産、把握のために必要。
名寄帳で、非課税明細も把握出来る場合が多いが、一部、非掲載の自治体もあるので要注意。 - 地籍図(地籍調査課)
地籍調査の成果として作成される地図。土地区画整理事業、土地改良事業などでも作成される。
法務局ではなく、市区町村の地籍調査課などが保管・交付。 - 建築計画概要書(建築指導課)
建物の用途・面積・築年数・敷地の面積や形状の確認に。ただし、管轄市町村によっては、保管期間が異なり、かなり古い物件のものが入手可能な場合もあれば、直近のものしかとれない場合もあります。また、依頼者が建築確認申請図面をもっている場合にはこの資料は不要です。 - 開発登録簿(開発審査課)
開発許可を受けた土地かどうかを確認。
建築基準法42条1項2号道路(=開発道路)の道路形状、幅員などを確認。 - 道路台帳(道路管理課)
公道の形状、幅員、管理者の確認。ただし、国道、都道、県道の場合にはそれぞれの資料を備えている土木事務所等に行かないと入手できない。 - 道路位置指定図(建築指導課)
建築基準法42条1項5号道路(=位置指定道路)の確認。 - 建築基準法上の道路種別の確認(建築指導課)
口頭で確認することが多いですが、図面をもらえる場合には入手しておきましょう。 - 道路境界確定図(用地課など)
正式な道路境界の位置を確認。 - 都市計画図・用途地域図(都市計画課)
建ぺい率・容積率・防火指定の確認。 - 上下水道台帳(上下水道課)
インフラ整備状況の確認。
※役所で入手できる資料もオンラインで入手及び確認ができるものもあります。
2-3. 民間サービスで取得できる地図資料
- ブルーマップ(地図会社/オンライン)
地番と住居表示の照合。オンラインでも閲覧・購入可能。 - 住宅地図(ゼンリン等/ネットサービス)
建物配置・現況利用の視覚的把握に有効。
3. 図面の使い分けと組み合わせのポイント
3-1. 地積測量図がない場合の代替手段
地積測量図がない場合は公図だけでは不十分な場合もあります。住宅地図やブルーマップとの照合、必要に応じて現地調査を併用(個人的には現地調査は必ず行うことを推奨)します。
例えば、登記簿や課税明細の面積と建築計画概要書の敷地面積が異なる場合には要注意です。筆全体を建物の敷地として建築確認をとっている場合には、概要書の敷地面積が実態に即していることがほとんどです。
また、公図には精度に差があり、特に旧土地台帳付属地図などの古い図面は現況と著しく異なるケースもあります。その場合は現地調査にて、間口、奥行、形状等を確認することをおすすめします。公図と現況が明らかに異なる場合には、縄延び・縄縮みの可能性もありますので、現況測量図の作成を土地家屋調査士・測量士に依頼することをお勧めします。
※現況測量は現地の境界標や塀・擁壁・道路など、現在の利用状況に基づいて行う測量のことで、登記簿や法的な境界に基づかないため、あくまで「現状の把握」が目的です。それに対して、確定測量は法務局備付の公図・地積測量図等に基づき、隣接所有者と境界を確定し、その合意のもとに行う測量のことです。財産評価のための資料としては現況測量で十分です。費用も現況測量のほうが安く納期も速いのが一般的です。
3-2. 複数の図面を組み合わせてリスクヘッジ
「公図 × 地積測量図 × 建築計画概要書」などを照合することで、形状・接道・評価単位を正確に把握します。特に、土地評価に慣れていない方は、使うか使わないかは後で考えるとして、入手可能なものはすべて集めておいても良いかもしれません。我々、不動産鑑定士も入手したけど、結局、あまり使わなかった資料は、結構あるものです。
4. よくある失敗と注意点
- 非課税財産の申告漏れ:私道などの非課税財産が相続財産に含まれていることに気づかない。
- 接道種別の未確認:路線価が付設している道路だけど、建築基準法上の道路でなかったことに気づかず、高い評価をしてしまった。
- 接道状況の未確認:対象地と道路の間には介在土地があり、実は道路に接していなかった。隣接しているのに出入りに使用していない私道などがある場合は要注意。
- 用途地域の誤認:評価補正率や法的制限に重大な影響を及ぼします。
5. 図面収集を専門家に依頼するという選択肢
評価対象地の特定や図面の整備には専門知識が求められます。不動産鑑定士等に依頼することで、評価資料の精度・網羅性を担保できます。
📌まとめ|図面・地図資料の取得先と役割一覧
| 資料名 | 取得先(担当部門) | 主な役割 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 法務局・登記部門 | 地目・面積・所有者の確認 |
| 公図 | 法務局・登記部門 | 土地の位置関係・筆の構成 |
| 地積測量図 | 法務局・登記部門 | 実測による形状・面積の把握 |
| 名寄帳・固定資産税課税明細 | 市区町村・資産課税課 | 課税・非課税財産の確認、所有財産の把握 |
| 地籍図 | 市区町村・地籍調査課 | 筆界・地番等の精度の高い情報(地籍調査済区域のみ) |
| 建築計画概要書 | 市区町村・建築指導課 | 建物の構造・築年数・敷地面積の確認 |
| 開発登録簿 | 市区町村・開発審査課 | 開発許可の履歴・制限状況の確認 |
| 道路台帳 | 市区町村・道路管理課 | 接道状況・幅員・道路種別の確認 |
| 道路位置指定図 | 市区町村・建築指導課 | 接道義務の充足状況を確認 |
| 建築基準法上の道路種別の確認 | 市区町村・建築指導課 | 接道要件を満たすかの口頭確認(資料入手可能な場合あり) |
| 道路境界確定図 | 市区町村・用地課 | 正確な境界線の確定情報 |
| 都市計画図・用途地域図 | 市区町村・都市計画課 | 建築規制・建ぺい率・容積率など |
| 上下水道台帳 | 市区町村・上下水道課 | インフラ整備状況の確認 |
| ブルーマップ | 民間(地図会社・オンライン) | 地番と住所の照合、周辺状況の把握 |
| 住宅地図 | 民間(ゼンリン等・オンライン) | 現況利用・建物配置の視覚的把握 |
図面の種類を理解して正確に評価を行うことで、相続税の申告精度が上がり、税務リスクも大きく軽減されます。
評価業務でお困りの際は、ぜひ専門家へご相談ください。
📚 関連記事
- 相続に強い東京の不動産鑑定士が教える土地評価の基本
─ 図面の読み解きや評価単位の考え方を基礎から解説。 - 囲繞地通行権がある土地の評価見直し事例
─ 地積測量図や通行経路の実地確認によって更正が認められた実例。 - 【2025年版】路線価の最新動向|東京都8.1%上昇、全国平均の約3倍の衝撃
─ 路線価図を使った土地評価に関する最新トレンドを解説。