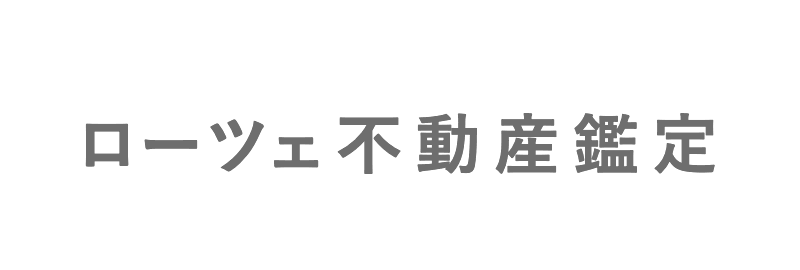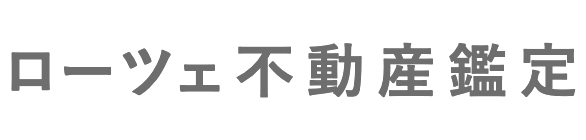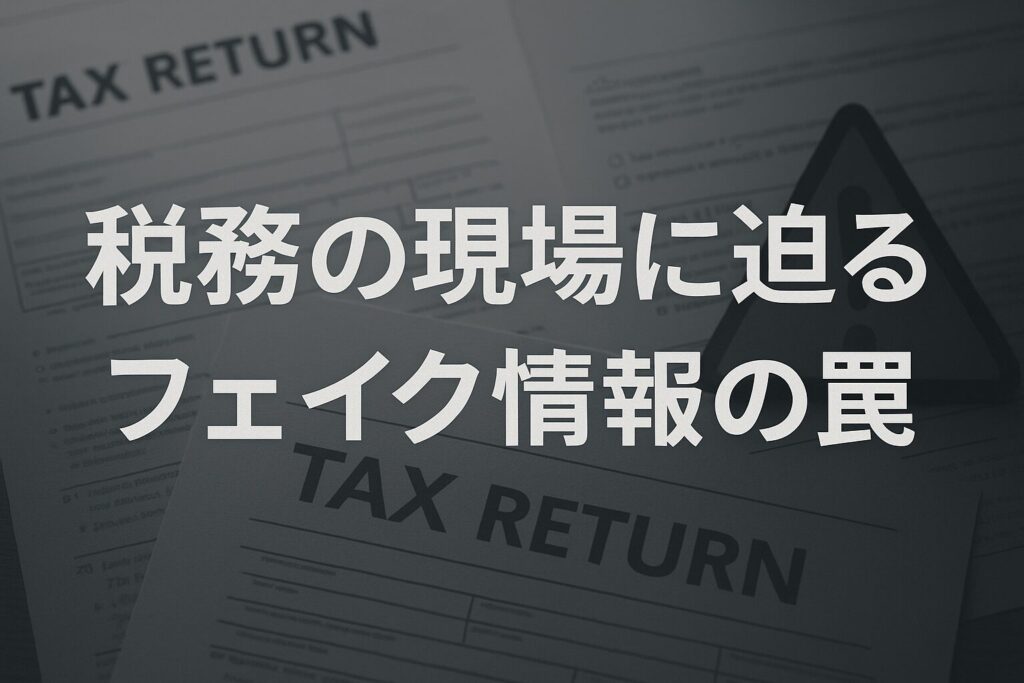
相続や譲渡に関わる不動産評価では、ネット上の“断片的な情報”が税務実務に大きな影響を与えることがあります。最近では「評価額を●割下げられる裏技」「税務署が教えてくれない節税法」など、真偽不明の情報が拡散され、納税者や税理士を混乱させています。今回は、資産税に精通した不動産鑑定士の立場から、税務におけるフェイク情報の特徴と、専門家がどう対応すべきかを解説します。
目次
1. なぜ今、税務実務にも「フェイク情報」が広がるのか?
1-1. ネット記事・YouTube・SNSの影響力
誰でも情報発信できる時代になり、専門的な話題でさえ動画やSNSで拡散されるようになりました。不動産や相続の分野も例外ではありません。しかし、それらの情報には出典が曖昧だったり、現場実務を無視した「受け狙い」の内容も目立ちます。
1-2. 一部の不動産業者や“節税コンサル”によるミスリード
「このやり方なら相続税が半分に!」といった甘い言葉で顧客を惹きつける手法は、不動産販売や節税ビジネスで一部見受けられます。税務調査に耐えうる根拠や、財産評価基本通達の理解を欠いた方法論は、かえってトラブルの火種となりかねません。
1-3. 「財産評価通達」の誤解と独り歩きする情報
通達はあくまで「画一的評価を可能にするためのルール」であり、現実の市場価格と必ず一致するものではありません。しかし、この基本が抜け落ち、通達評価を「絶対」とする誤解や、逆に「必ず時価より高い」とする極論が横行しています。
| 要因 | 影響度(主観的スコア) | 解説 |
|---|---|---|
| ネット記事・SNS・YouTube | 5 | 出典不明・断片的な情報が拡散しやすい |
| 一部の不動産業者・節税コンサル | 4 | 現実離れした節税スキームを推奨 |
| 通達評価に関する誤解・極論 | 3 | 通達=絶対視、または時価乖離を誤解する極端な言説が目立つ |
2. よくあるフェイク情報の実例
2-1. 「借地権をゼロ評価にする裏技がある」
借地権の評価において、「無償返還届出書を出せばゼロで良い」といった主張があります。確かに通達にはそうした規定がありますが、実際には契約の内容や利用実態、過去の取引履歴を踏まえた判断が不可欠です。形式要件だけを整えても、実態に即していなければ否認されるリスクがあります。
2-2. 「無道路地なら必ず評価を大幅に下げられる」
接道義務を満たしていない無道路地であっても、通行権や建築許可の特例が存在する場合、評価がそれほど下がらないこともあります。訴訟で囲繞地通行権が認められた場合には、路線価評価の減額が予想以上に無いこともあります。
2-3. 「時価より安く売れば相続税対策になる」
建物を法人に“安く”売ることで贈与税や相続税の対策になるという話も、価格の妥当性を証明できなければ、逆に「みなし譲渡」や「受贈益課税」の対象になります。とくに同族間取引では鑑定評価等の客観的根拠が必須です。
2-4. 「鑑定評価を使えば何でも安くできる」
これは鑑定評価への誤解を生む危険な表現です。鑑定評価は市場実態や法的制約、取引事例など多くの要素を加味して行われる専門的手続きであり、「都合の良い金額を出してくれる」ものではありません。税理士や納税者にとっても、適正な納税と税務調査対策のためには、信頼できる評価根拠が必要です。
3. フェイク情報が招く3つのリスク
3-1. 納税者の過大期待 → 後のトラブル
「ネットにはこう書いてあった」「YouTubeで〇〇先生が言ってた」と、根拠なき期待を持つ納税者が増えています。期待が裏切られた際に、不満の矛先が税理士や関係者に向くケースも少なくありません。
3-2. 税理士の信頼低下 → 税務調査リスク
十分な裏付けのない節税を提案した結果、否認されたり、更正の請求が却下される事態になれば、顧客からの信頼を損ねるだけでなく、税理士業務のリスク管理上も重大な問題となります。
補足:問題が“起きなかった”=“正しかった”とは限らない
中には「こういうやり方で何の問題もなかった」「過去に否認されなかったから大丈夫だった」と語るケースがありますが、それはあくまで“偶然、問題にならなかった”にすぎません。
税務署の担当者が見落としていたり、申告内容全体の中で優先順位が低く、たまたま深くチェックされなかったという可能性も十分にあります。
その方法が本当に正しかったのかどうかは、「否認されなかった」事実だけでは判断できません。むしろ一度うまくいったことを根拠に繰り返すことには大きなリスクがあります。専門家としては、常に“再現性”と“正当性”のある根拠を持って対応することが不可欠です。
3-3. 更正の請求で否認される可能性
フェイク情報に基づく評価変更の試みは、提出書類や添付資料に説得力がなければ通りません。適切な評価手法や鑑定評価による裏付けがなければ、更正の請求は認められず、徒労に終わるケースもあります。
4. 専門家が取るべき3つのスタンス
4-1. 「情報の出所」を精査する姿勢を伝える
顧客には「ネット情報の多くは一般論であり、実際には個別の事情が優先される」ことを説明し、専門家として出所や根拠を重視している姿勢を見せることが信頼構築につながります。
4-2. 相続評価に強い不動産鑑定士との連携を提案
土地評価に特化した不動産鑑定士と連携することで、通達と鑑定の“すき間”に対応できます。とくに無道路地や私道負担地、権利関係が複雑な土地では、鑑定評価によって救われるケースも多いです。
4-3. 通達評価と鑑定評価の違いを顧客に正しく説明する
評価通達は税務上のルールであり、時価とは必ずしも一致しません。ケースによっては通達を補完する形で鑑定評価が必要になることもあることを丁寧に説明することで、顧客の納得と理解を得やすくなります。
第4章:専門家が取るべき3つのスタンスと対応策
| 専門家のスタンス | 具体的な対応・効果 |
|---|---|
| 情報の出所を精査する姿勢を伝える | ネット情報の一般性と限界を顧客に説明 → 信頼感の向上 |
| 相続評価に強い不動産鑑定士との連携を提案 | 無道路地など複雑な土地に柔軟対応 → 税務リスク軽減 |
| 通達評価と鑑定評価の違いを正しく説明する | 時価と通達評価の違いを伝え誤解を防止 → 顧客の納得を得やすく |
5. まとめ “正しい情報をつなぐ”のも専門家の仕事
相続・譲渡など大きな金額が動く分野では、“一見お得な話”ほど慎重な判断が必要です。税理士や不動産鑑定士といった専門家が、正しい情報を咀嚼し、依頼者にとってベストな選択肢を見つけていくことが、これからの実務に求められています。
フェイクに流されず、事実と専門知識に基づいた判断を貫くことこそ、専門家の真価です。
相続や譲渡に関わる不動産評価では、ネット上の“断片的な情報”が税務実務に大きな影響を与えることがあります。最近では「評価額を●割下げられる裏技」「税務署が教えてくれない節税法」など、真偽不明の情報が拡散され、納税者や税理士を混乱させています。今回は、資産税に精通した不動産鑑定士の立場から、税務におけるフェイク情報の特徴と、専門家がどう対応すべきかを解説します。