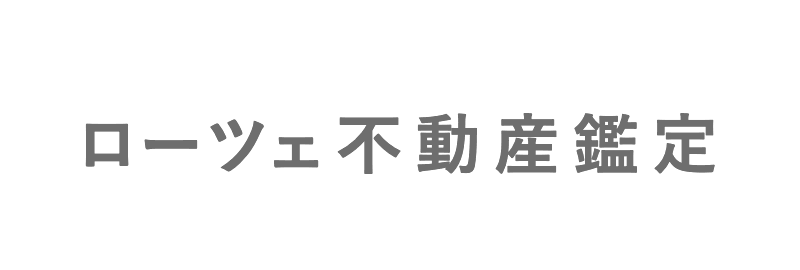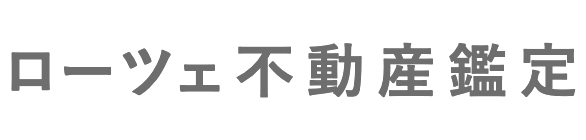「この物件、いま空室があるけど、ずっと賃貸目的だったから100%賃貸割合で大丈夫ですよね?」 これは、相続税評価の現場でよく耳にする一言です。しかし、この「100%」という数字が、国税当局にとっては軽くない問題であることを忘れてはなりません。
貸家建付地の評価において、土地の評価額が大きく減額されるか否かは、借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 によって決まります。つまり、「賃貸割合」が50%か100%かの違いだけで、評価額は何千万円単位で変動することも珍しくありません。
本記事では、国税不服審判所で争われた以下の2つの裁決──
- 平成21年3月25日裁決(以下「21‑3‑25裁決」)
- 平成20年6月12日裁決(以下「20‑6‑12裁決」)
を比較しながら、「一時的空室」とは何か、賃貸割合を100%とするためにどのような主張・証拠が求められるのかを、不動産鑑定士の視点から解説します。
目次
1.評価通達26と「賃貸割合」──制度的な背景
1-1.貸家建付地の評価構造
貸家建付地とは、借家の敷地となっている宅地であり、評価通達26では以下の式により評価します。
自用地価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
ここで言う「賃貸割合」とは、通常、賃貸されている部分の床面積割合を指します。しかし、評価通達26の(注)では、「課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分については、賃貸されていたものとみなして評価する」と明記されています。
つまり、一時的空室であれば、賃貸中とみなされ、賃貸割合に含めることが可能となります。問題は、その「一時的」の定義です。
1-2.2つの裁決の比較ポイント
| 裁決番号 | 空室率 | 空室期間 | 募集活動 | 評価結果 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年3月25日裁決 | 50%(2棟合計8室中4室が空室) | A1棟:4室が1年9か月以上空室A2棟:5室が9か月以上空室 | 賃料の引き下げ実施あり。ただし広告・媒介契約等の記録なし | 賃貸割合50%に修正 |
| 平成20年6月12日裁決 | 20%(20室中4室が空室) | 最短2か月、最長1年11か月(すべて相続後に成約) | 媒介契約・募集広告・成約実績などを提示 | 賃貸割合100%が認容 |
2.21‑3‑25裁決──空室は「賃貸目的でなかった」と判断された事例
2-1.事案の概要
この裁決では、相続開始時点で、被相続人が所有していた2棟の共同住宅(合計8戸)のうち、4戸が空室でした。納税者側は、すべての部屋を賃貸目的としていたため、賃貸割合100%と主張しました。
しかし、審判所はこれを退け、空室部分については賃貸用でなかったと判断し、賃貸割合は50%にとどめるべきとしました。
2-2.主な否認理由
(1)空室の長期化と「一時的」とは言えない実態
A1棟の4室はすべて1年9か月以上、A2棟でも5室が9か月以上空室となっていました。これだけの長期間空室が継続している状況は、評価通達26にいう「一時的な空室」とは到底言えず、審判所も「継続的な空室」と評価しました。
(2)募集活動の実態が不明確
相続開始前に賃料の引き下げは実施されたものの、媒介契約や募集広告、内覧の記録など、具体的な募集行為の証拠は提出されませんでした。審判所は「積極的な募集活動が行われていたとは認められない」としています。
3.20‑6‑12裁決──空室でも「一時的」として賃貸割合100%が認められた事例
3-1.事案の概要
この裁決では、1棟20戸の賃貸マンションのうち4戸が空室でした。空室期間は最短2か月、最長で 1年11か月で、すべて相続発生後に新たな入居者との契約が成立しています。
3-2.審判所が「一時的空室」と判断した根拠
(1)媒介契約・募集広告・募集図面を提出
納税者側は、空室部分について不動産業者との媒介契約書、実際に作成された募集広告・図面等を提出しており、入居者の募集活動が行われていた事実が明確でした。
(2)成約実績が全戸にあり、申告後も速やかに賃貸継続
相続開始時に空室だった4戸は、すべて相続後に賃貸借契約が締結されており、最短で2か月、最長でも1年11か月の間に全室が成約されています。すなわち、空室部分は申告時点でも明確に賃貸の用に供される予定であったと評価されました。
(3)賃貸目的の所有と賃貸継続の意思の一貫性
この物件はもともと全室賃貸目的で取得されていたものであり、空室となっていた部分も含めて、引き続き賃貸として活用される意思が明確でした。審判所もこの点を重視し、評価通達26の(注)にいう「一時的に賃貸されていなかった部分」として扱うことを認容しました。
4.両裁決の比較と実務上のポイント
4-1.「一時的空室」の認定に必要な3要素
裁決事例に基づく実務的判断ポイントは、以下の3要素で整理できます。
- ① 賃貸意思の継続性が明確であること:媒介契約、オーナーの意思表明、賃貸方針の継続が重要。
- ② 入居者募集の履歴が示されること:広告媒体、業者とのやり取りの記録など、外部に可視化されていたか。
- ③ 成約や申し込みの実績があること:空室が動いていたという事実があれば非常に強い証拠になる。
この3要素が揃えば、「一時的空室」として100%評価が認められる可能性が高まります。
《コラム》「一時的」ってどのくらい?──1か月の壁は絶対か?
貸家建付地の「賃貸割合」に関しては、国税庁が公開した**資産評価企画官情報第2号(平成11年7月29日)**において、
以下のような判断要素が示されています:
① 課税時期前に継続的に賃貸されていたか
② 退去後すぐに募集が行われたか
③ 空室期間中に他用途に使われていないか
④ 空室期間が一時的か(例:1か月程度)
⑤ 課税時期後の賃貸が一時的でないか
ここで示された「1か月程度」という表現は、あくまで一例であって、必ずしも厳格な条件を意味するものではありません。
実際、20-6-12裁決のように1年以上、空室であっても、「一時的空室」と認定された事例も存在します。
👉 重要なのは期間の長短そのものではなく、空室に至る経緯・賃貸意思の継続性・成約実績など、事実全体からの総合的判断です。
4-2.実務での資料準備と税理士・管理会社の役割
単なる言い分では通用しません。実務で準備すべき証拠資料には以下があります。
- 賃貸意思の裏付け:媒介契約書、業務委託契約書、所有者の説明文書
- 入居者募集の証跡:チラシ、ポータル掲載履歴、問い合わせログ
- 成約・申込の記録:契約書、申込書、内見記録、入居予定日など
4-3.税理士と管理会社の連携で備える「証拠化」
空室が一時的であることを主張するには、証拠を残す文化が重要です。
- 税理士の役割:ヒアリング、証拠の収集、申告書への記載・整理
- 管理会社・業者の協力内容:広告スクショ、反響データ、内見記録、広告費の記録など
評価の正しさではなく、立証の備えが評価を分ける現実を意識することが求められます。
| 判断要素 | 具体的な確認資料 | 実務上の留意点 |
|---|---|---|
| 賃貸意思の継続性 | 媒介契約書、業務委託契約書、所有者の説明文書 | 相続開始前後の意思の一貫性を示す |
| 入居者募集の履歴 | チラシ、ポータルサイト掲載記録、問い合わせ履歴 | 広告媒体の種類や掲載期間も記録しておく |
| 成約・申し込み実績 | 賃貸借契約書、申込書、内見記録、入居予定日 | 1戸でも成約履歴があると有利な証拠になることも |
5.まとめ──空室=100%は危険!評価の「意図」と「証拠」を忘れずに
空室がある=減額できない、というわけではありません。 しかし、“空室でも賃貸用です”という主張は、裏付け資料がなければ通りません。
税理士や不動産鑑定士としては、以下の点に留意しておく必要があります。
- 賃貸意思の継続性を客観資料で示せるか
- 相続開始後も募集活動が継続されているか
- すでに成約実績があるかどうか
- 管理会社等の業務記録が残っているか
一時的空室の判断は「税務署によって異なる」場合もあり、評価リスクを最小限に抑えるには、実務と裁決例に基づく事前整理が重要です。
「空室があるが賃貸割合100%で申告してよいか?」という相談は、相続税申告の現場で意外と多い論点です。税務署対応を見越して、証拠資料をどう準備すべきか──必要に応じてご相談ください。