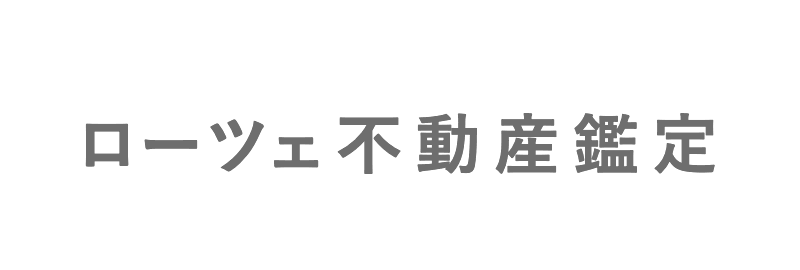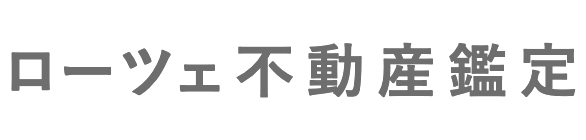相続税の土地評価で多く使われる「財産評価基本通達」ですが、すべての不動産に適用できるとは限りません。とくに無道路地のような特殊な土地では、通達だけでは適正な時価を示せず、納税者が不利益を被るケースもあります。
今回は、大阪地裁において通達評価が否定され、不動産鑑定評価が全面的に採用された事例をご紹介します。鑑定士の立場から、税理士・相続人にとって実務上押さえておくべきポイントを整理します。
目次
1.無道路地と通達評価の補正
1-1. 無道路地とは?
建築基準法により、土地には原則「幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務があります。これを満たさない土地が「無道路地」です。
建物の新築・再建築ができず、流通性が著しく低下するため、実勢価格も大幅に下がるのが一般的です。
1-2. 財産評価基本通達の補正限界
通達では、無道路地に対して最大40%の減額補正(通達20-2)が認められていますが、実際の土地条件によっては、この補正ではまったくカバーできない場合もあります。特に、接道確保のための高額な工事費が必要なケースでは、通達補正が現実の市場価格に追いついていない状況がしばしば見られます。
💡無道路地の通達評価や補正率の基本については、以下の記事もご参照ください:
👉 相続財産に無道路地がある場合の土地評価と注意点
📌 補正率は最大40%ですが、それでも市場実勢に比べて評価が高すぎるケースは多く存在します。実態に即した見直しが必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接道義務 | 建築基準法で、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない |
| 無道路地とは | 接道義務を満たさない土地であり、建物の新築・再建築ができないため流通性が低い |
| 通達補正(通達20-2) | 無道路地に対して最大40%の減額補正が認められている |
| 補正の限界 | 実際には通路開設費用などがかかる場合、40%補正では市場価格に追いつかないことがある |
2.税務争訟に至るまでの流れと壁
2-1. 異議申立て〜訴訟へのプロセスと費用負担
相続税の課税に納得できない場合、すぐに訴訟を提起できるわけではありません。次の手続きを段階的に踏む必要があります。
1.税務署への異議申立て(費用無料)
2.国税不服審判所への審査請求(費用無料)
3.それでも是認されない場合に限り、地方裁判所で訴訟提起(費用+時間的負担)
ただしこのプロセスで重要なのは、是認率の低さです。
・異議申立ての是認率:約3〜5%
・国税不服審判所:約10%未満(実質数%)
つまり、行政内で納税者の主張が認められることはほとんどないのが現実です。裁判に進めば、弁護士費用や印紙代などがかかり、費用面・時間面の負担が一気に増大します。
| ステップ | 手続先 | 費用 | 是認率 |
|---|---|---|---|
| ① 異議申立て | 税務署 | 無料 | 約3〜5% |
| ② 審査請求 | 国税不服審判所 | 無料 | 10%未満(実質数%) |
| ③ 訴訟提起 | 地方裁判所 | 弁護士費用・印紙代など必要 | 裁判所の判断次第 |
2-2. 今回争点となった丙土地の状況
相続財産に含まれていた「丙土地」は建築基準法上の無道路地で、再建築には900万円以上の通路開設費用が必要とされました。申告時は通達補正を適用して549万円で評価されましたが、納税者側は実態にそぐわない過大評価だと主張しました。
3. 大阪地裁が通達評価を否定した理由
3-1. 不動産鑑定評価の提示
納税者側は不動産鑑定士の意見書を提出し、建築不可・利用困難・著しい市場性の低さを反映したうえで220万円の時価評価を提示しました。
3-2. 裁判所の認定
大阪地裁(平成29年6月15日判決)は、以下のように判断しました。
「評価通達では接道義務を満たしていないことを十分に反映することができず、適正な時価を算定できない“特別の事情”がある。」
つまり、通達評価が妥当ではないと認定され、鑑定評価がそのまま採用されました。更正処分の一部が取り消される結果となりました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 争点となった土地(丙土地) | 建築基準法上の無道路地/通路開設に900万円以上必要 |
| 申告時の評価額(通達評価) | 549万円(通達補正を適用) |
| 鑑定士による評価額 | 220万円(建築不可・市場性の著しい低下を反映) |
| 裁判所の判断 | 通達評価は適正時価を示せず“特別の事情”があると判断 |
| 結果 | 通達評価は否定され、鑑定評価が採用された(更正一部取消) |
4.実務上のリスクと回避策
4-1. 通達による画一的評価の危うさ
財産評価基本通達は、一定の基準に基づき公平性を保つことを目的とした制度ですが、あくまで**“標準的な画一評価ルール”に過ぎません**。
現実の土地は千差万別であり、とくに無道路地・不整形地・がけ地などでは、通達による一律補正では実勢価格を適正に反映できないケースが少なくありません。
❗【注意】通達補正の「40%」は“上限”に過ぎません。
👉 実態によっては、それでも著しく過大評価となるケースがあります。
たとえば、通達では「無道路地補正率」を最大40%までしか適用できませんが、
✔ 実際の接道状況が極端に悪い
✔ 通路確保に多額の費用がかかる
✔ 建築不可で市場流通性が著しく劣る
といった場合には、補正後の評価額でも著しい過大評価となってしまうのです。
このような過大評価が申告段階で見過ごされると、
後になって相続人が更正の請求を余儀なくされたりするリスクが生じます。
特に、評価明細書を第三者(税務署や審判所、裁判所)に説明する際、
通達評価しかないと「なぜこの評価額なのか?」に説得力を持たせづらいという問題もあります。
4-2. 早期対応の有効性と限界
無道路地など通達評価の限界が明らかな土地では、相続申告時点で不動産鑑定評価を併用しておくことが有効です。
ただし、早期に鑑定評価を取得していたとしても、税務署や国税不服審判所では通らず、最終的には訴訟に至った可能性も否定できません。
それでもなお、専門性の高い評価資料が早期に用意されていれば、税務署内の議論や国税不服審判所での審理もより具体的に進みやすく、裁判所においても納税者側の主張がより説得力をもって伝わることになります。
つまり、「通らない可能性があるとしても、評価の正当性を示す武器としての鑑定評価」は、争いの局面全体を有利に運ぶための戦略的資料なのです。
| リスク・課題 | 問題点の具体例 | 対応策 |
|---|---|---|
| 通達評価の画一性 | 土地の実情を反映できず過大評価となる可能性 | 不動産鑑定評価を併用する |
| 補正率の限界(最大40%) | 通路開設に高額な費用がかかる場合、補正が追いつかない | 評価時に個別事情を反映させる |
| 接道困難・工事費用の無視 | 通達は接道工事の具体的コストを考慮しない | 鑑定評価で費用控除や市場性の低下を明示 |
| 建築不可による市場性の低下 | 市場流通性が著しく劣る土地にも画一的補正 | 建築制限の影響を正確に評価に反映 |
| 評価明細書の説得力不足 | 税務署・裁判所での説明が困難になるケースあり | 鑑定評価を資料 |
5.税理士・相続人が取るべき実務対応
5-1評価に不安がある土地は、専門家に相談を
通達評価がそのまま妥当とは限らない土地、たとえば無道路地・がけ地・極端な不整形地などでは、「特別の事情」に該当し、通達に代わる評価方法が認められる余地があります。
また、市街地山林についても、利用状況や地勢、周辺の実勢取引を踏まえれば、通達による近隣宅地比準方式ではなく、純山林価額比準方式を採用した方が、より低廉な適正時価を導けるケースもあります。
評価額が相続税に与えるインパクトが大きい場合、申告時点で不動産鑑定士の意見を交えて適正性を担保しておくことが、後々の否認や修正リスクを未然に防ぐ実務的な対応策となります。
5-2. 訴訟リスクを減らすための“予防評価”
不動産鑑定評価は、調査報告書として文書化されており、評価理由・手法・類似事例などが定量的かつ客観的に示されています。
こうした第三者性のある評価書があることで、税務署への説明はもちろん、万一訴訟になった場合でも説得力を持って主張を展開できます。
実際、税務署や審判所では「通達評価を形式的に守っているだけでは判断できない」という場面もあります。
そうした場合に備え、最初から予防的に評価書を添えて申告・相談しておくことで、税理士の立場も守られ、依頼者からの信頼も高まるはずです。
| 実務対応のポイント | 具体的な対策内容 |
|---|---|
| 評価に不安がある土地は専門家へ相談 | 無道路地・がけ地・不整形地などは早期相談が重要 |
| 特別の事情がある場合は通達に代わる評価方法の検討 | 評価単位や地勢・地目・利用制限などを個別に考慮 |
| 相続税への影響が大きい場合は申告段階で鑑定評価を取得 | 専門家意見を加えることで否認リスクを軽減 |
| 訴訟リスクに備えた“予防評価”の活用 | 鑑定評価書で第三者性・説得力ある資料を残す |
🔗 判決資料リンク(国税庁)
判決文や国税庁による要約は、下記よりご確認いただけます。
📄 大阪地裁 平成29年6月15日判決(税務訴訟資料 第267号)(順号13024)
👉 国税庁 税務訴訟資料(2017年)
まとめ:この事例が教えてくれること
建築できない無道路地を通達の上限「40%補正」で評価すると、納税者の立場からは不利な評価となることもあります。
しかし、本件では、不動産鑑定士による評価を通じて、裁判所は「通達では時価を捉えられない」と判断。
結果、330万円近い評価減が認められ、相続税の減額に成功しました。
この判決は、通達に過信せず、土地の実態を反映した評価を行うことの重要性を示しています。
そしてそれを実現できるのが、不動産鑑定評価の場合も多々あります。無道路地の評価については、通達だけに頼らず、鑑定評価という選択肢も視野に入れるべきです。特に「相続 無道路地 評価」「通達評価 限界」「不動産鑑定士 評価」などで検索される実務家にとって、本事例は極めて示唆に富むものです。
関連記事のご紹介
「【囲繞地通行権がある土地の評価見直し事例】接道制限などが原因で更正が認められた実例紹介」の記事はこちらからご覧いただけます。
👉 囲繞地通行権がある土地の評価見直し事例|接道制限が原因で更正が認められた実例紹介