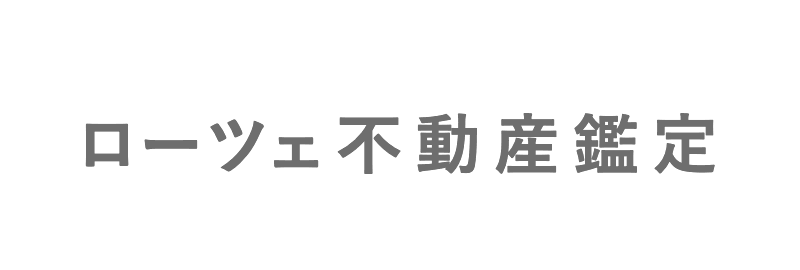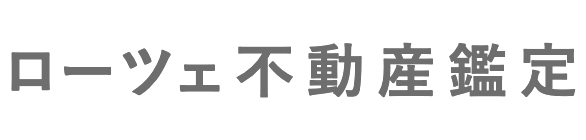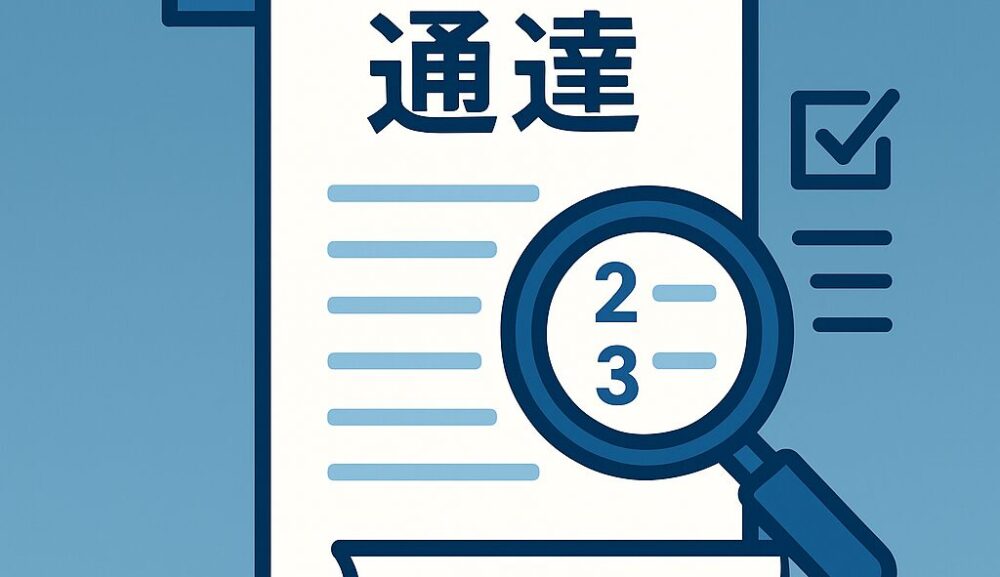相続税や贈与税における土地評価の実務では、「財産評価基本通達」の理解が不可欠です。なかでも第二章第一節(通則)は、評価の出発点とも言える基本的ルールを定めており、「評価単位」「地目判定」「権利の取扱い」といった根幹事項が示されています。
税理士やその事務所職員が、評価通達を正しく解釈しないと、過大評価や過少評価による申告ミスにつながるおそれも。
この記事では、不動産鑑定士の視点から、第二章第一節をわかりやすく、かつ実務に即して整理・解説します。
目次
1. 通達第二章第一節が定める評価ルールの全体像
土地の評価においては、以下の4つの基本視点が示されています。
- 1.1 地目の判定(第7項)
- 1.2 評価単位の確定(第7-2項)
- 1.3 地積の基準面積(第8項)
- 1.4 権利の種類別の評価(第9項)
評価実務では、この順に沿って「評価の出発点」を正しく設定することが重要です。
2. 第7項:地目の判定と一団評価の基本ルール
通達では、土地を課税時点での現況に基づき地目判定し、異なる地目が一体利用されている場合には主たる地目で一団評価することを認めています。
2-1. ファミリーレストランとその駐車場
- 登記: 店舗部分が宅地、駐車場部分が雑種地
- 現況: 駐車場は店舗利用の一部として不可分
- 評価: 一団の宅地として評価するのが合理的
2-2. ゴルフ練習場(打ちっぱなし)
- 構成: クラブハウス(宅地)+練習場(雑種地)
- 現況: 練習施設として一体的に利用
- 評価: 主たる利用が雑種地であるため、一団の雑種地評価が妥当
2-3. 企業の研究所と緑地(公開空地)
- 構成: 研究施設の敷地(宅地)+周囲の緑地(雑種地)
- 現況: 来訪者通路や避難スペースとして一体利用
- 評価: 宅地として一団評価するのが合理的
3. 第7-2項:評価単位の考え方と実務判断
土地評価における最小単位(評価単位)は、地目によって異なります。
| 地目 | 評価単位の考え方 |
|---|---|
| 宅地 | 利用単位(複数筆でも一団評価可) |
| 農地 | 1枚の農地(市街地農地は一団評価も可) |
| 山林・原野 | 原則1筆(市街地山林等は一団評価も可) |
| 雑種地 | 利用実態に基づき、一団評価も可能 |
✅「登記簿上の筆」と「評価単位」は一致しないことに注意!
4. 第8項:採用面積は登記面積でよいのか?
原則として、課税時点での現況面積を基に評価します。登記面積と異なる場合は、実測図等を優先します。
4-1. 採用面積の根拠とするために有用な資料一覧
登記簿面積と現況面積が異なるケースは多く、特に実測図がない場合には、以下のような資料を複合的に活用することで、評価に足る面積の信頼性を補完できます。
| 資料名 | 入手先 | 用途・補足 |
|---|---|---|
| 地積測量図(=確定測量図) | 土地家屋調査士、法務局 | 境界確定済みの正式な測量図。評価・申告において最も信頼性の高い根拠となる。但し、作成が古いものは信頼性が劣るものもある。 |
| 現況測量図(仮測量図) | 土地家屋調査士、測量士、売主等 | 境界未確定の段階で現地測量を行った図面。現況面積の把握や登記面積との乖離確認に有効。 |
| 建築計画概要書 | 市区町村(建築指導課) | 建築確認申請に用いる敷地求積図が添付されていることが多く、登記面積と異なる場合の補正根拠として重宝。 |
| 公図 | 法務局 | 面積の精度は低いが、敷地形状や筆界の目安確認に活用可能。 |
| 地籍図 | 各市区町村(地籍調査実施自治体) | 地籍調査済区域においては、実測に基づく形状・面積が反映されており、現況把握に有効。 |
| 上下水道・道路台帳 | 各市区町村 | 間口幅、接道長、形状などの補完資料として有用。 |
🔍 補足: 複数の資料を突き合わせ、現地確認と併せて評価判断を行うのが実務上の鉄則です。
4-2. 建築計画概要書は「信頼できる現況面積」のヒント
建築確認申請時に提出される敷地求積図の面積は、測量図がない場合の有力な補完資料になります。
✅ 特に登記面積と大きく異なる場合、補正評価や説明資料の添付が望まれます。
5. 第9項:土地の上の権利の評価とは?
土地そのものではなく、土地に係る“権利”を評価対象とするケースも少なくありません。
| 評価対象 | 内容 |
|---|---|
| 借地権・地上権 | 建物所有目的などの利用権 |
| 区分地上権 | 上空・地下の限界利用など |
| 永小作権 | 農地耕作のための使用権 |
| 耕作権 | 農地の賃借権(農地法制限あり) |
| 占用権・温泉権 | 公共施設や温泉の引湯利用など |
✅ 所有権とは異なる評価方法を要するため、通達だけでなく実務判断が求められます。
6. まとめ|実務に活かすための着眼点
財産評価基本通達の第二章第一節は、「土地評価の起点」として非常に重要です。 一見単純に見える「地目」「面積」「権利」も、実務では例外的・複雑なケースが頻出します。
💬 不動産鑑定士からのアドバイス
- 評価単位や地目判定においては、「登記」だけで判断せず、現況利用や機能的関連性を読み解くことが肝心です。
- 実測図が無い場合でも、「建築計画概要書」や「道路台帳」などの周辺資料を活用すれば、信頼性の高い評価が可能となる場合があります。
- 複雑な権利関係や一団評価の可否などで判断に迷う場合は、不動産鑑定士等の専門家の関与が適正評価と税務リスク回避につながります。
✅ よくある質問(FAQ)
Q. 評価単位は登記の筆ごとに判断すればいいの?
A. 必ずしも登記の筆とは一致せず、現況利用や一団の機能性に基づく判断が必要です。不明確な場合は専門家の助言が不可欠です。
Q. 登記簿面積と実測面積が違う場合、どちらを優先すべき?
A. 原則は現況面積です。実測図などの信頼できる資料がない場合は、建築計画概要書や上下水道台帳などを併用して補正判断を行います。
Q. 宅地と雑種地が一体利用されている場合、どのように評価しますか?
A. 通達では、主たる地目に従って「一団評価」することが認められています。たとえば店舗と駐車場が一体利用されていれば、全体を宅地として評価することが妥当です。
Q. 測量図が手元にない場合でも、評価はできますか?
A. 可能です。地積測量図がない場合でも、建築計画概要書、道路台帳、公図、現況測量図など複数の資料を組み合わせて、現況に即した地積判断を行うのが実務の基本です。
関連記事
➡ 基礎から押さえたい方は、相続に強い東京の不動産鑑定士が教える土地評価の基本もご覧ください。
➡ 評価の根拠条文から理解したい方は、相続税評価の要点と実務|財産評価基本通達総則1-2の意義と通達評価の読み解き方も参考になります。
➡ 資料の詳細な解説は、相続税の土地評価で使う『収集資料(主に図面関係)』まとめをご覧ください。
💡 財産評価基本通達の原文を確認したい方は、以下の国税庁ページもご参照ください。
→ 国税庁|財産評価基本通達 第二章第一節(評価の通則)