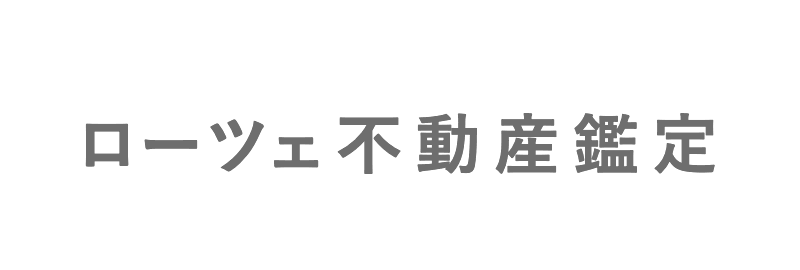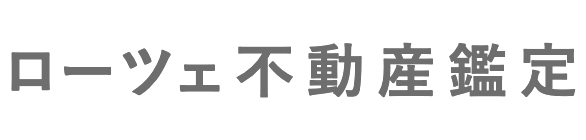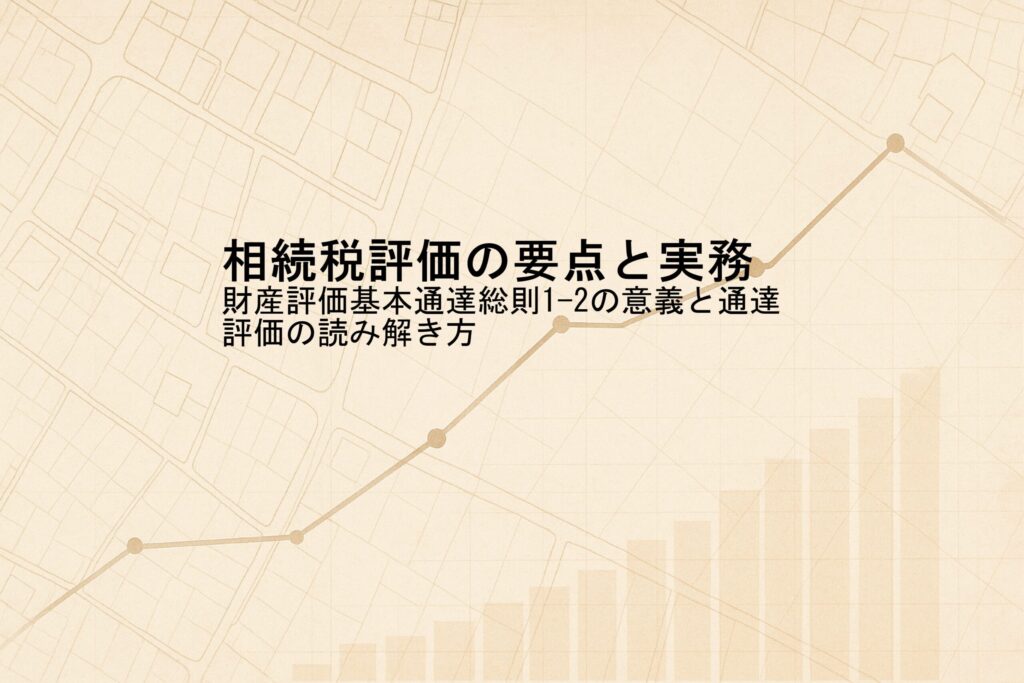
相続税の土地評価では、「財産評価基本通達 総則1-2」に基づき通達評価額を「時価」とみなす運用がされています。
しかし実務では、通達評価額と市場価値が乖離するケースや、通達の補正だけでは適正な課税価格に至らない場面も少なくありません。
本記事では、総則1-2の意義と通達評価の基準性・限界、さらに鑑定評価・総則6の位置づけまで、税理士・税理士事務所の職員の方が現場で読み解くべきポイントを解説します。
目次
1.総則1-1と総則1-2および相続税法22条の時価
1-1.相続税法22条「客観的交換価値」とは
相続税法22条は「課税時期における客観的交換価値」で課税財産を評価すると定めています。これは自由市場で合理的条件の下で成立する市場価値、すなわち鑑定評価基準の正常価格と同趣旨です。
1-2.総則1-2が示す二層構造の意義
総則1-2は「時価とは、この通達の定めによって評価した価額による」と規定しています。つまり相続税法の市場価値を統一的に迅速評価するルールが評価通達です。
👉 相続税法の「時価」=市場価値(正常価格)
👉 通達評価額=標準化された時価
という二層構造を正しく理解することが実務の出発点です。
1-3.総則1-1(評価単位)の整合性の重要性
評価単位(地目・一団・権利関係等)がずれると、市場価値・通達評価・鑑定評価の比較が成り立ちません。最初に評価単位を一致させる確認が必要です。
2.通達評価の性質と市場価値との差が生じる理由
2-1.通達評価の設計思想と限界
通達評価は全国一律の公平課税・迅速処理を目的とした簡便法です。路線価方式や倍率方式を用い、標準宅地を前提に画一的な補正率で調整します。その結果、個別性を細部まで反映できない限界があります。
2-2.乖離しやすい典型例
| 例 | 乖離の主因 |
|---|---|
| 無道路地 | 接道補正が粗く建築不可リスクが十分反映されない |
| 大規模傾斜地 | 一律の造成費控除が実費との差を生む |
3.鑑定評価基準の価格種類と税務評価の接点
3-1.正常価格の定義
正常価格とは、
市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。この場合において、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場とは、以下の条件を満たす市場をいう。
(1)市場参加者が自由意思に基づいて市場に参加し、参入、退出が自由であること。
なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益を最大化するため次のような要件を満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し、行動するものとする。
① 売り急ぎ、買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。
② 対象不動産及び対象不動産が属する市場について取引を成立させるために必要となる通常の知識や情報を得ていること。
③ 取引を成立させるために通常必要と認められる労力、費用を費やしていること。
④ 対象不動産の最有効使用を前提とした価値判断を行うこと。
⑤ 買主が通常の資金調達能力を有していること。
(2)取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするような特別なものではないこと。
(3)対象不動産が相当の期間市場に公開されていること。
3-2.正常価格を平たく言えば|相続税評価での市場価値基準
正常価格とは、売主・買主とも特別事情がなく、自由で公平な条件で成立する標準的な市場価値のことです。
上記1でも触れましたが、相続税法22条の「課税時期の客観的交換価値」と基本的に同趣旨です。
3-3.限定価格の定義|隣接地併合・分割売買に関連する評価
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
3-4.特定価格の定義|再生法・更生法での評価
特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合
(2)民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
(3)会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合
3-5.特殊価格の定義|文化財・公益施設の相続税評価
特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。
応じて検討される例外的評価ルールです。適用には証拠資料の積み上げが不可欠です。
4.乖離是正の実務フロー
4-1.通達内補正の徹底確認|相続税土地評価の基本実務
通達評価では、側方加算等を除けば、路線価×面積の評価額がその土地の評価額の最大値であり、側方・二方路線加算以外の補正率はすべて減価補正です。
したがって、減価補正を正しく適用し、減価要因を最大限活用して評価額の適正化を図ることが第一歩です。
4-2.正常価格に基づく鑑定評価の活用|税務調査・更正請求の現場で
通達補正で足りない場合、正常価格に基づく鑑定評価は以下の目的で活用します。
✅ 通達評価と市場価値の乖離理由を可視化・定量化
・通達評価額と正常価格の差額(乖離額)を明示
・その差が生じた具体的理由(例:接道制限、極端な地形、法的規制)を詳細に説明
✅ 必要資料を一体的に整備
・鑑定評価書(正常価格の算定根拠)
・図面(公図・測量図・位置図)
・写真(現況の物理的制約の証拠)
・除去費・造成費等の試算資料(見積書や工事費根拠)
✅ 評価単位・前提条件を通達評価と一致させる
・評価単位(地目・一団・権利範囲)を揃え、比較可能性を確保
・鑑定評価の前提条件(最有効使用・制約条件)を明確化
✅ 提出のタイミング
・申告時:添付資料として合理性を主張
・調査時:通達評価との差異説明の根拠資料
・更正請求・審査請求時:主張補強資料
このように、鑑定評価書は単なる価格提示ではなく、通達評価との差異の合理的理由を「可視化・数値化・文書化」するツールとして活用する のが実務上の正しい姿勢です。
4-3.総則6の趣旨と適用手順|通達評価限界時の救済ルール
総則6は次のように定められています:
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」
これは、通達評価が市場実態と乖離し、課税の公平性を著しく損なう場合の例外的救済条文です。
🌟 実務上の留意点
✅ 総則6適用のハードルは高い
適用事例は極めて限定的です。鑑定評価書だけではなく、その乖離理由の合理性を裏付ける証拠資料(図面、写真、見積根拠等)の積み上げが必要です。
✅ 総則6は最後の選択肢
総則6に頼る前に、通達内補正で調整を試みるのが原則です。
4-4.期限内申告から争訟までの実務フローと鑑定評価の活用|税理士実務の手順
🌟 期限内申告段階
申告の段階で通達評価に基づく課税価格が著しく市場実勢価値と乖離する場合、正常価格による鑑定評価書を添付し、適正な課税価格を申告します。
👉 期限内申告では通達の定めによれない場合、適正な評価額(正常価格)での申告が求められます。
鑑定評価書は、あくまでその合理性と根拠を税務当局に示す補強資料であり、通達評価を覆す手段ではなく、正当性を説明するためのツールです。
🌟 調査段階での活用
税務調査で通達評価との差異が指摘された場合、正常価格の鑑定評価書、図面、現況写真、合理的理由資料を提示し、乖離理由を具体的に説明します。
🌟 更正請求以降の流れ
課税価格が過大だったと判明した場合:
1️⃣ 更正の請求
鑑定評価書・図面・根拠資料を添付し、過大課税の是正を求めます。
2️⃣ 管轄税務署への異議申立て
更正の請求が棄却された場合、異議申立てを行い、課税の誤りを主張します。
3️⃣ 国税不服審判所への審査請求
異議申立てでも認められない場合、審査請求を行います。
4️⃣ 必要に応じて訴訟
審査請求後も解決しない場合、訴訟に進みます。
🌟 【フロー表|相続税評価の乖離是正 実務の流れ】
| ステージ | 実務の流れ | 実務のポイント・必要資料 |
|---|---|---|
| 期限内申告 | 通達補正を徹底適用し評価額を調整 → 正常価格による鑑定評価を添付するか検討 | 減価補正・鑑定評価の適否を検討/現況図・測量図・写真等を添付 |
| 調査段階 | 調査で否認された場合 → 異議申立て → 審査請求 → 必要に応じ訴訟 | 調査段階で鑑定評価・根拠資料を提示/乖離理由を明確化 |
| 更正の請求ルート | 鑑定評価を使わず申告 → 後から乖離判明 → 更正請求 → 異議申立て → 審査請求 → 訴訟 | 鑑定評価書・補正根拠資料を添付し合理性を主張 |
注記: 総則6は、通達の定めによる評価が著しく不適当と認められる場合に、各段階(更正請求・異議申立て・審査請求・訴訟)で必要に応じて検討される例外的評価ルールです。国税庁長官の指示に基づく評価が求められ、適用には証拠資料の積み上げが不可欠です。
まとめ|“通達”と“市場価値”の二刀流で評価精度を高める
- 二層構造を腹落ちさせる
- 相続税法22条の時価=市場価値(正常価格)
- 評価通達額=標準化された時価(最大値)
→ 路線価 × 面積をスタートラインに、減価補正で現実に近づける──これが相続税評価の基本フレーム。
- 総則1を“地図”に、総則6を“非常口”に
- 総則1-1が示す評価単位を合わせなければ比較そのものが成り立たない。
- 総則1-2は通達価格を「時価」とみなす根拠。
- どう補正しても通達が機能しないとき初めて 総則6 を叩く――これが王道の順番。
- 通達内補正を“全部盛り”する
- 側方・二方路線加算以外は減価補正。
- 不整形・間口狭小・奥行価格・造成費控除など、適用漏れと二重控除の確認を徹底。
- この段階で市場価値に近づけば、後工程(鑑定評価・訴訟)のコストを抑えられる。
- 正常価格の鑑定評価は“可視化ツール”
- 申告・調査・争訟の各ステージで、通達評価額と市場価値の差額・原因を数値と図面で示す。
- 評価単位・最有効使用・前提条件を通達と揃えることで説得力を担保。
適正課税を守るカギは、“通達で行ける所まで行く” と “正常価格で乖離を証明する” の二刀流。
税理士と鑑定士が評価単位と価格種類を共通言語に、段階的・証拠主義で攻めることが実務最強の戦術です。
相続税の土地評価実務では、通達評価を尽くした上で、必要に応じ鑑定評価や総則6を適切に使い分け、課税価格の適正化を図ることが税理士の重要な役割です。評価乖離の是正は、通達内補正の確認から始め、鑑定評価書や合理的根拠資料を段階的に積み上げることが成功のカギとなります。